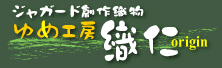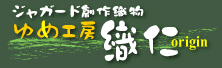| このページでは、今までに新聞・雑誌等で取り上げられたオリジン・(株)出口織ネームの記事を掲載しています。 |
探訪 チャレンジ企業3 1999年 7月 1日 『商工かが.のと』
夢のある新商品開発に全社員一丸
鶴来町・(株)出口織ネーム
新製品は容易に開発できるが、新商品は容易に開発できないという考えがある。それは、如何にアイデアを出した新製品であっても、末端の消費者が消費し使ってくれなければ、商品といえず製品の段階にとどまっているからである。それ程までに新製品から新商品に至る距離は近くて遠いのである。
沈滞する繊維業界にあって新商品を開発し、異色の存在として活躍しているのは、鶴来町にある株式会社出口織ネームである。
何が異色かといえば従業員16名の中、男性は2名のみで残り全員女性である。しかも、彼女達は、社長が自慢する程優れており、各自責任をもって仕事をこなし、十分まかせられることが第一。第二は、新商品企画や開発に当たっては、女性ならではの意見を出し、そのため、的確に時代に合った新商品を開発できること。第三は、営業は社長の奥さんをはじめ3人で担当し、物産展や展示出店会で全国を駆け巡り、販売現場におけるお客の声を吸収し、次回の新商品開発に生かすなど実に商品化の取り組み連携は見事になされている。
しかし、何といっても社長出口勉さんの資性は素晴らしく毅然としている。その一は織ネームは何時まで経っても主役となれる商品でない。一度この織ネームの技術を使って主役となる商品を作ってみたいという強い願望を持ち続け新商品開発に挑戦して来たこと。第二は、異業種交流に参加し、交流仲間から企業経営について真摯に学び実践していること。第三は、生産は小口のロットで多種多様に徹していること。第四は、糸づくりから最終の商品段階まで自社で仕上げ、商品に対し、責任と誇りをもって消費者へ提供していること。第五は、自社製に対応するため、独自考案の機械や新鋭機械の導入を積極的に行い、今やちょっとやそっとで誰もまねの出来ない設備を持つまでになり、これらを駆使して夢のある新商品づくりに余念がない。
こうした中から産まれた商品は、匂袋、コースターの小物から卓布、バッグ、壁掛け等多彩であり、全て商品として売れて行く。特に壁掛けは白山襲織と命名し、優れたデザインと共に繊維製品の新しい分野を開いたといえよう。また最近では、刺繍と見紛う如きジャカードによる織の上に手縫い刺繍をドッキングさせるなど新商品を開発し、異業種との成果を上げるなど、新商品にかける夢は拡大続くばかりである。
もの造りが好きでたまらないこの姿勢が、経営という枠組みの中で活かされ、しかも社員全員が責任をもって参加するところに、製品から商品への遠い道程を見事短縮し、不況にもかかわらず元気印の企業となっているのである。
|
繊維にかける 1999年 2月 8日 『毎日新聞』
繊維にかける
服の裏に縫い付けられる織ネーム。ふだんは気に留めないが、ほんの数㌢角にブランド名や素材、製造国などの文字がくっきりと織り出されている。複雑で緻密な模様織りの技術が凝縮した布だ。
京都・西陣が発祥の織ネームは現在、福井、石川の2県で作られている。織ネームの技術から派生したリボン作りも盛んで、いわゆる細幅織物の一大産地だ。創業50年の「出口織ネーム」(石川県鶴来町)は、その中でも異彩を放つ。水に溶ける素材で織った釣り用の疑似餌(ぎじえ)、袋織りで試作した人工血管、Jリーグ人気で火がついたひも状ブレスレットのミサンガ・・・・・・。細く細かく織る技を応用し、アイデアを凝らしたさまざまな品を、出口勉さん(50)は作ってきた。「父の代は注文通りにネームを織っていましたが、私は自分にしかできないものを作りたかったのです」
偽造防止用にブランドマークの内側に隠し文字を入れたり、細幅専用機よりも複雑な色柄ができる広幅織機で、ネームが織れるよう工夫もした。仕上がりの美しさに、有名ブランドやキャラクターなど、ネームにも高い質を求める顧客がついた。縫い付ける本体の素材を聞いて、違和感のない質感にするなど、ネーム一枚でもやることはたくさんある。撚糸機からカッターまで独自仕様そろえ、一貫生産体制も整えた。
「とにかく、もの作りが好き」という出口さんの思いは、「付属品」の枠を越え始めた。広幅織機をもともとの2メートル幅のままに使い、服地を織ってみた。早速、イタリアのブランド、ミッソーニのバッグ用記事の注文が入った。2年前からはタペストリーや匂い袋を売り出した。何色もの糸を使って絵を織り描く、縫い合わせずに織りで袋を作る、といった織ネームの力を存分に発揮した「本体」作りに、出口さんは魅せられた。
「織ネームは製造過程がよく知られていないので、発注者から細かく指定されることがない。その分、こちらが好きなように作れる自由があります。いろいろな織り方を試せた。それがいまに生きています」。付属品という制約、太くても10㌢という幅の限界の中で鍛えた出口さんの布作りは、限りなく広がる。 【上杉恵子】
|
きらら輝く女 1998年 12月20日発行 『山女vol.12』
毎日毎日をいとおしむ。
自分をみがく。
いつも前向き、
きらら輝く発展途上人。
そんなING進行形の女性を、
白山麓に訪ねます。
今回は、
白山襲織 ゆめ工房「織仁」の
鶴来町の出口智子さん。
プロフィール
小松市生まれ、今年で結婚25周年を迎える。襲織の分野で、2年程前から設備や技術力の確保が実現し、ゆめ工房 織仁を設立。現在企画開発部コーディネーターとして躍進中。
(株)出口織ネームから独立し、いままで存在しなかった、オリジナリティの高い作品を創り上げる「織仁」。この工房のコーディネーターである出口智子さんを訪ねた。大勢のスタッフと共に試行錯誤を繰り返し、ただひたすら創る、その力はどこから湧いてくるのだろうか。
・・・・・・襲織と一口にいわれても何であるのか想像がつかない。まず襲織の「襲」とは何なのか意味を伺った。
「襲(かさね)色目という言葉があって、いろの違うものを重ね合わせたり、組み合わせたりすることによってあるモノを演出していくという意味があるんです」
糸は先染めの色を掛け合わせながら柄出しをしていく。多くの色糸を同じラインで繰り返し織り重ねることによって独特の色が創り出され、形となっていく。出来上がった生地自体厚みがない。極力糸も細くして、柔らかい質感をかもしだしている。
・・・・・・(商品を見ながら)色目が落ち着いていて、とてもいいですね。
「自然界の植物や景色に近い色目を出し、表現しています。中間色やぼかしをふんだんに使って、おちつきや柔らかさを表現しています。
・・・・・・自然が基本となっているんですね。
「そうかもしれません。以前からよく山菜採りや白山麓を散策するんですが、その度自然界に魅せられて、いつかこれを表現できないかと思ってきました。ここにしかない、こだわったデザインと形。特に白山郷を出発点と考え、『白山襲織』ゆめ工房
織仁とつけました」
白山という言葉が肩書きに入っているのはそんな思いの表れだ。出口さんにとって「ゆめ工房織仁」はまさに自己の表現なのである。
・・・・・・「鶴来」という名を入れたモノがあるんですが。
「私達の町をもっと知ってもらいたい。気軽に遊びに来て下さい、といった意味もあって、あえて入れてたのもあります」
自然そのものをモチーフとし、糸を重ねて色の深みを出している。「まるで我が子のようにかわいい」と智子さんの表情からひとつひとつの作品に、確固たる思いがこめられている。
出口さんは小松市に生まれ、鶴来に嫁いで二十五年になる。当時、もちろん織りについては全くの無知で、ご主人につき、考える暇なく働いたそうだ。今では息子さんも大きくなり、事業に加わっている。「こんなに早く一緒に仕事をしてくれるとは思いませんでしたね」とうれしそうに語る出口さんの表情から笑みが浮かぶ。
・・・・・・商品を創っていく中でのご苦労は?
「商品は一人ではできません。特に当工房の作品は形を決めることから始まって、色、柄、大きさ、仕立て、付属品や包装にいたるまでトータルで考えるからとても大変ですね。スタッフやお客さんを交えた大勢の人の思いや、いろんな声を参考に毎日試作・研究しています」
・・・・・・この作品はどこにあるんですか?
「展示会形式で出展・販売しています。委託販売で卸をするということは今のところ考えていません。テナントや店舗として販売していくという考えはあります。商品だけを納めて、後は任せるといった形はとりたくないですね。一番やりたかったことの理由は創る方と使われる方とのやりとりの中でモノが出来上がっていくということ。本当に面白いモノは何であるか掘り下げて、皆がほしい・味わいたいものの声を大切にし商品にしていく。これがたまらなく楽しいんです」
・・・・・・今後の抱負を聞かせてください。
「未知の世界ですからね、何が生まれるのか、モノの見方もかわってくるし。『これほしかったのよ』と言われるようなものを開発できたら。意外なところにヒントがあるんじゃないかと思いますね」
自分たちの住む白山麓で、あたりまえのように見ている四季の表情や関わる人々の声すべての色を襲(かさ)ね、一枚の織りとなる。そこからは自分たちのつくりたいものへ近づこうとする純粋で真摯なものづくりの姿が見えてくる。出来上がっていく作品、そしてこれからの人生にどんな色を重ねていくのか、とても楽しみである。
|